TS-BASE 受発注
2024.01.22
EDI連携とは何か?注目される背景・メリット・デメリットを詳しく紹介

目次
EDI連携とはそもそもなんだろう、と調べている方もいらっしゃると思います。EDIは受発注書や契約書など、取引先とのやりとりに必要な書類を電子化して取引を行うことです。連携時には、メリットとデメリットをあらかじめ把握してから運用することが大切です。
本記事では EDI連携について、概要・注目される背景・メリット・デメリットを紹介します。
EDI連携とは
EDI(Electronic Data Interchange)は「電子データ交換」を意味する言葉です。
電話回線・インターネットを通じて、取引先企業と契約書・受発注書・納品書・請求書など様々な業務書類をやり取りするためのシステムです。
EDIでは従来の紙ベースの文書処理から電子データへ移行しているため、作業効率の向上や人的ミスの削減にも繋がります。
業務帳票の電子化が進む近年では、 企業間取引の効率化を促進するためにもEDIは不可欠といえるでしょう。
企業間取引とは?円滑に進めるためのポイントもあわせて解説しています。

Web EDIとは
Web EDI連携とは、インターネット回線を使用したEDIの一つの形態です。従来のEDIシステムは電話回線の利用でしたが、WebEDI ではインターネットを通じて取引情報をやり取りでき、初期費用・運用のコストを大幅に削減します。
Webブラウザで利用できるため、ソフトウェアやサーバー機器なども不要です。手軽に始められることが大きな利点と言えるでしょう。
Web EDIは低コストで利用しやすく、中小企業からも人気が高いです。導入すれば、企業はより効率的に取引を管理できるでしょう。
Web EDIについてもっと詳しく知りたい、という方はこちらもあわせてご覧ください。
Web EDI徹底ガイド:メリットから注意点、注目の受発注システムも紹介!

EDI連携への注目が高まる背景
ここからは、EDI連携の注目が高まる背景を3点紹介します。
多様な働き方への対応
新型コロナウイルスの影響でリモートワークが急速に拡大しました。
オフィスだけでなく自宅や他の場所からでも円滑に業務を行う必要性が高まっており、働く場所の多様化が進んだことで、EDIの導入が注目されています。
EDIは、従業員がどこにいても取引を継続できる柔軟性を提供しています。不測の事態があっても、業務の中断を最小限に抑え、安定したビジネス運営を支援する重要なツールとなるのです。
EDI導入は、現代の多様な働き方に対応する上で不可欠で、企業のデジタル変革を推進できる重要なステップと言えます。
DX推進
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、ビジネスの競争優位性を確保するために、デジタル技術を活用して新たな価値を創出することです。
DX推進の一環としてEDIの普及が進んでいます。
EDIは取引書類をデジタル化して、インターネットを介して迅速かつ正確に情報を交換することを可能にし、紙ベースの作業から電子化への移行を促進します。これにより、データ処理の速度と正確性が向上し、企業はより迅速な意思決定と効率的なビジネス運営を実現できるのです。
上記背景から、EDIは今後もますます重要性を増していくと予想されます。
DX推進の必要性について、実際の効率化事例とともにご紹介しています。

導入ハードルが低い
従来は高価な専用システムと複雑な設定が必要でしたが、近年のEDIは低価格で簡単に導入・運用できるようになりました。特に中小企業にとって大きなメリットのため、幅広い業種で EDI が採用されています。
WebベースのEDIソリューションは、初期投資の削減はもちろん、簡易な操作性や柔軟なカスタマイズができることも特徴です。
企業のデジタル変革を加速させるためにEDI導入のハードルの低さは重要であり、今後も高まることが予想されます。
EDI連携の種類
EDIには、個別 EDI と標準 EDI があります。それぞれ紹介していきます。
個別EDI
個別EDIとは、取引先ごとに通信形式・識別コードをカスタマイズできるEDIのことです。特定の取引先と、特殊な要件・形式が必要な場合に適しています。
独自の業務プロセスやシステムに合わせた環境を構築でき、企業は柔軟かつ効率的な取引ができます。また、独自要求にも対応しているため、パートナー間ともより密接で、効率的な取引関係を築けるでしょう。
標準EDI
標準EDIは、さまざまな企業間でのデータ交換を安定して効率的に行うためのEDIです。取引規約・運用ルール・データ形式・フォーマットなどといった、ルールが標準化されています。
標準EDIには特定の業界に特化された業界 VAN があります。業界内共通で、商品コード・取引先コードなどが決まっています。そのため、同じ VAN を利用する他社とよりスムーズなデータ交換が可能です。
標準EDIの導入により、企業は効率的な取引プロセスを実現し、ビジネスの効率化と競争力の強化を図れます。多くの企業にとってアクセスしやすく、ビジネス運営の基盤として広く利用されています。
EDI連携のメリット
ここからはEDI連携のメリットを紹介していきます。
人的ミス防止
1つ目のメリットは、人的ミスの防止です。
EDIはデータの転記ミスや書類の紛失、郵送の遅延といった人的エラーを大幅に削減でき、手作業による業務書類の記入・作成・郵送なども不要となります。
EDI連携をすれば、データ管理がシステム上で行われるようになり、データ入力の正確性が向上します。
システムによる自動化処理は、手作業に比べて誤りの可能性が極めて低く、企業間のコミュニケーションにおける信頼性と効率性を高められるのです。
人的ミスの防止はEDI連携の重要なメリットの一つであり、企業は時間とコストの削減、業務の効率化を実現し、全体的なビジネスの品質を向上できます。
受発注業務における人的ミスを減らす工夫を、他にも紹介しています。
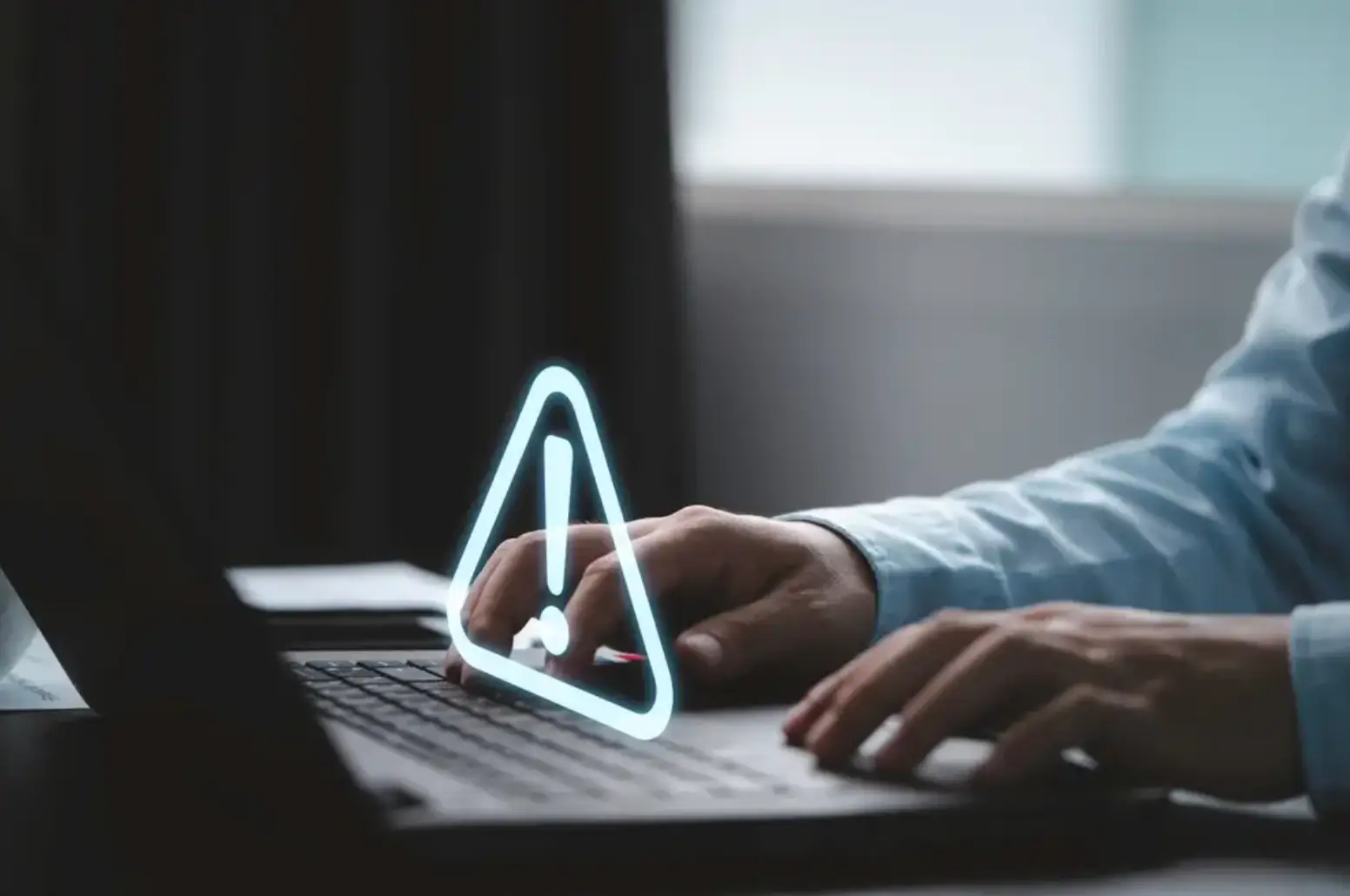
作業効率化
EDI連携を実施すれば、書類の記入・印刷・郵送などの手間が大幅に削減できるなど、作業効率化に大きなメリットをもたらします。
従来の紙ベースの文書処理では、時間と労力を要する必要がありましたが、EDIでは、電子化により従来のプロセスを簡略化できます。
また、担当者は手作業による煩雑な文書処理から解放され、より重要な業務に集中することも可能です。
データの即時交換で情報の遅延もなくなり、迅速な意思決定ができるのです。さらに、文書追跡と管理を容易にすることで、業務の透明性と正確性を向上できます。
作業効率化により、企業は競争力を高め、ビジネスの全体的な生産性を向上できるでしょう。
用紙コスト削減
用紙コストの削減も、EDI連携のメリットの一つです。
EDIを導入すれば、紙代・印刷代・郵送代などのコストを削減できます。電子化したデータで取引するため、物理的な文書が不要となるからです。
企業は紙の使用量を減らし、それに伴うコストも削減できるため、EDIの重要性は今後も高まるでしょう。
EDI連携でありがちなデメリット
ここまでEDI連携の概要と種類、メリットを紹介しました。それでは、デメリットとして何があるのでしょうか?ここからはEDI連携でありがちなデメリットを紹介していきます。
非互換のケースも
EDI連携の避けて通れない問題の一つに、取引先との非互換性があります。
異なるフォーマットやプロトコルを使用しているなど、システムやサービス間の互換性がない場合、企業は取引先とのスムーズなデータ交換を行えなくなります。
そのため、企業が新しい取引先との関係を築く際や、既存の取引先がシステムを変更した際に、EDI連携の効率性や利便性を損なう可能性があるでしょう。その結果、追加の調整やカスタマイズが必要となり、時間とコストがかかってしまいます。
上記デメリットを克服するためには、業界標準に準拠したEDIソリューションの選択や、柔軟なカスタマイズが可能なシステムの導入が必要です。
トラブル発生の場合も
EDI連携では、取引先との間で「いずれかのシステムでトラブルが発生すると、取引がストップする」といったリスクがあります。
なぜなら、EDIシステムが双方の企業間で密接に連携しているため、一方のシステムに問題が生じるともう一方にも影響を及ぼす可能性があるためです。
したがって、EDI連携を採用する際は、システムの安定性やトラブル時の対応計画を十分に検討することが重要です。
コスト対効果を得られない場合も
EDI連携するためには、初期コストがかかるため、取引量や取引相手が少ない企業にとって、コスト対効果を十分に得られない場合もあります。
特に、小規模な企業や取引頻度の低い企業では、EDIシステムの導入と維持に関わる費用が、利益を上回る可能性もあるでしょう。
そのため、自社の取引量や取引相手の数を考慮した上で、投資の見返りが期待できるかどうかを慎重に評価してから、EDIを導入することが大切です。
EDIは企業間取引を効率化するためのシステムです。取引量や取引企業が少ないなど、場合によっては費用対効果を十分に得られない可能性もあることに注意しましょう。
EDI連携で業務を効率化しよう
EDI連携は、企業間の文書やデータ交換を電子化し、取引プロセスを効率化するシステムです。
人的ミス削減や作業効率化、コスト削減の効果を期待できますが、取引量や取引相手が限られている企業にとっては、導入と維持のコストがその利益を上回る可能性があります。
そのため、自社の現在の取引状況、取引先のシステムを考慮した上で、費用対効果を慎重に評価してから導入しましょう。
-

TS-BASE編集部さん
運用実績10年以上・お取引件数300件以上を誇る「TS-BASE シリーズ」の編集部です。 現場で得た知見を活かし、実務に役立つヒントやノウハウをどんどんご紹介していきます!!
導入をご検討の方は
こちらから



-
サービスの紹介資料や
お役立ち資料は
こちらから -
導入のご検討やその他ご相談は
こちらから





